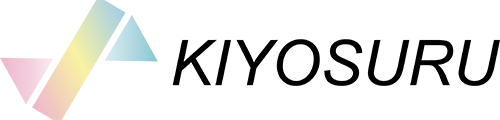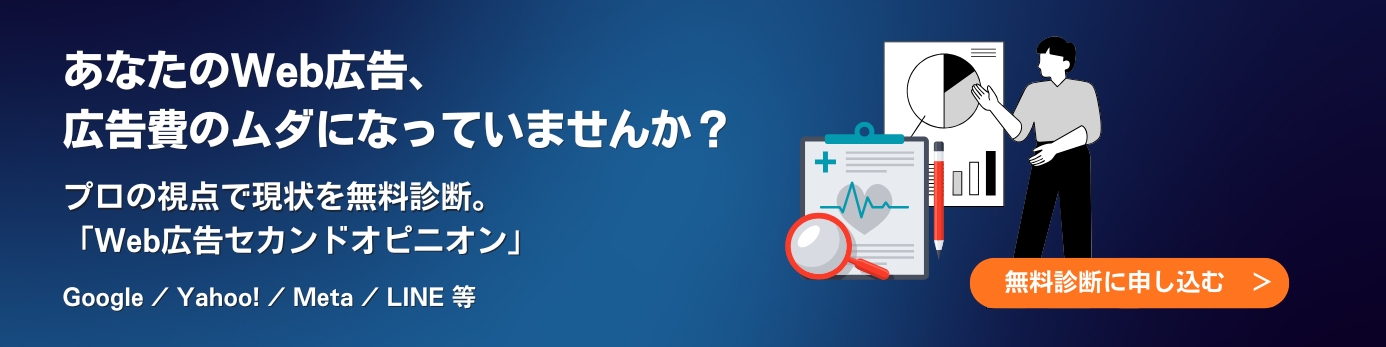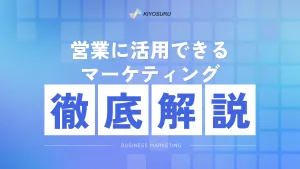生成AI利用率3割未満の日本、キャズムを超えられない理由
総務省の令和7年版情報通信白書によると、日本で生成AIを利用した経験がある人はわずか26.7%でした。アメリカや中国に比べて極端に低い数値です。
なぜ日本では生成AIの普及が進まないのでしょうか。「普及の壁(キャズム)」という視点から、日本市場の課題と生成AIが進むべき方向性について解説します。
日本の生成AI利用率が世界最低レベルの理由とは?
日本で生成AIを一度でも使ったことがある人の割合は26.7%にとどまっています。アメリカの約7割、中国の約9割と比べても、非常に低い水準といえるでしょう。
この背景には、日本人特有の「新しいものに対する慎重さ」や「失敗を避けたい」という文化が関係していると考えられます。
スマートフォンが登場した際にも、日本では欧米より普及が遅れました。生成AIでも同様に様子見の姿勢が強く、それが利用率の低さにつながっているのかもしれません。
新技術に対して慎重になりやすいことは、日本市場の特徴のひとつです。これは人口構成上、年齢が高い人達が多い高齢化問題も大きく関係しているのではないか?と推測されます。
生成AIは検索エンジンの「補助ツール」にとどまっている
一方、日本の2倍近いユーザーが利用するアメリカの方ではどのように活用されているのでしょうか?
アメリカでは検索エンジンを月に10回以上使う人が86%に上る一方で、生成AIを月に10回以上使う人は21%にとどまっています。
よく「生成AIを使うから、検索エンジンを使わなくなっている」と言われていますが、実際の数字を見るとそうではありません。生成AIは検索エンジンの代替ではなく、あくまで補助的な役割にとどまっているのがアメリカの実情です。
日本での活用方法は?
日本ではどのように生成を使われているのでしょうか。これはNTTドコモの研究所が調査したものですが、生成AIの利用について「検索・情報収集」「テキスト作成・要約」「翻訳」と答えた方が多くありました。
(参考:生成AI、「どんなものか知らない」が約半数--NTTドコモ調査 - ZDNET Japan)
この生成AIの利用については、ほぼ検索エンジンやGoogleその他のサービスでできることがほとんどです。「テキスト作成・要約」や「仕事や学業の自動化・効率化、サポート」といった使い方は生成AIならではの使い方かと思いますが、まだまだ多くはありません。
このように生成AIでの使い方がほぼ検索エンジンやその他既存サービスの使い方と同じであることが、普及のブレーキになっている可能性があります。
本質的な課題解決こそがキャズムを超えるカギ
生成AIが今後さらに普及していくためには、検索や翻訳などの既存機能では対応しきれない領域に焦点を当てる必要があります。
特に注目したいのは、仕事や学業における業務効率化のサポートです。具体的な課題を解決できるような活用こそが、生成AIの真価を発揮する分野といえるでしょう。
また、日本の労働市場で長年の課題とされる「3K(きつい・汚い・危険)」職の負担軽減や人手不足の解消に貢献できるかどうかも、重要です。そもそも人間が機械に頼ることは「人間ができないことをやってもらう」のと並行して「面倒なことを機械にやってもらう」というのがあります。洗濯機・掃除機などまさにそうして出てきたものです。
生成AIは便利なツールから、社会課題を解決する存在へと進化していけるかが問われています。マーケティングの視点から見ても、生成AIでしか実現できない価値を明確に打ち出すことが、普及のカギになるといえるかと思います。
まとめ
- 日本の生成AI利用率は3割未満で先進国でかなり低い
- アメリカのAI利用率の伸び方は鈍化している
- キャズムを超えられなければ、このまま衰退する可能性
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
兵庫県伊丹市出身
2006年、立命館大学経営学部卒業後、パソコンソフトの卸売会社、総合商社子会社に就職し、2008年に独立。
2011年頃からSEO対策・アフィリエイト用の文章制作から、独学でリスティング広告やアクセス解析、SNS広告などを学び、サービスを展開。
短期大学の情報処理講師や職業訓練校のWebサイト制作クラス・ECマーケティングクラスなどで講師を担当。
現在は株式会社キヨスル代表取締役として、Webマーケティングをデザインすることでクライアントのビジネスに貢献する。
その他の記事
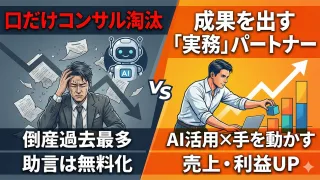 Webマーケティングラジオ2026年1月19日「口だけコンサル」は淘汰される?過去最多の倒産から見るコンサルティングの未来
Webマーケティングラジオ2026年1月19日「口だけコンサル」は淘汰される?過去最多の倒産から見るコンサルティングの未来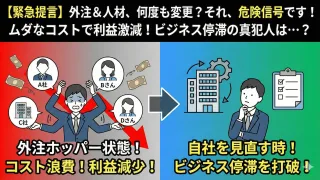 BtoB向け施策2026年1月12日成果が出ないのはパートナーのせい?「外注ホッパー」が陥るビジネスの罠
BtoB向け施策2026年1月12日成果が出ないのはパートナーのせい?「外注ホッパー」が陥るビジネスの罠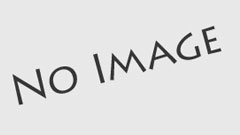 お知らせ2026年1月5日2026年ご挨拶
お知らせ2026年1月5日2026年ご挨拶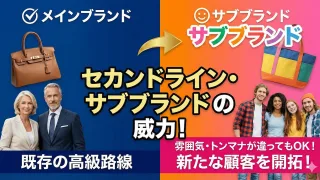 Webマーケティングラジオ2026年1月5日「セカンドライン」で考える新商品・新事業
Webマーケティングラジオ2026年1月5日「セカンドライン」で考える新商品・新事業