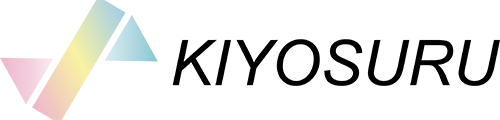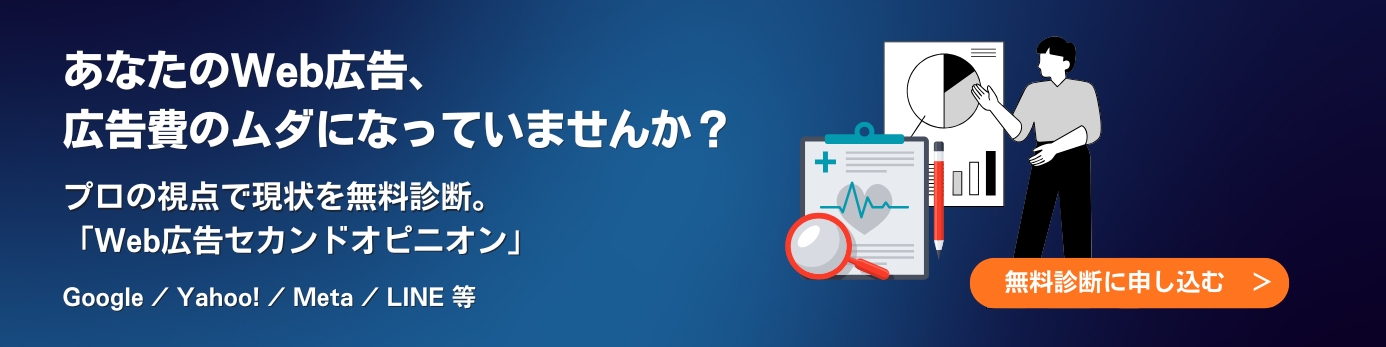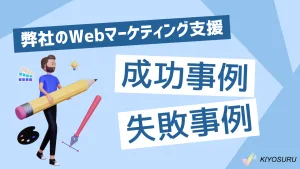経済学に賛成?反対?経営者の考え方との違い
経済学者がいろいろな提言をしているのはSNSやニュース番組などで見るかと思います。経営者としても賛成する部分も多いのですが、簡単にできない部分もあるな、と感じています。
ニセコの事例~なぜ給与を上げられないのか
日本の円安もあり、インバウンドが活況です。特に北海道のニセコは多くのスキー客が来るということで、注目されています。ニュースでもニセコでは時給が上がっていて、1600円以上で東京以上に高くなっているという報道もあります。介護事業などでは給与を上げることができず、倒産するケースも増えているようです(参考:ニセコのリゾート時給2千円超 地元から悲鳴「人採れない」 住民生活に影響も:北海道新聞デジタル)。
こういったケースでは経済学者は「時給を上げていけばいい」という主張が出ます。人が足りないなら時給を上げれば、ニセコに他の地域からもやってくる、だから給与を上げればいいという主張です。介護事業は人手不足で倒産してしまうくらいですが、なぜ給与を上げられないのでしょうか?経営者はどう考えているのでしょうか。
実は介護事業は売上の上限が決まっています。どのような施設で広さがどのくらいなのかで報酬が決まっているのです。インバウンドの旅行業は努力次第で売上を上げられます。今までのプランよりもラグジュアリーにしたり、新しい付加価値をつければ、客単価を増やすこともできるでしょう。しかし、介護事業にはそういった事ができないのです。給与はあくまで売上・利益から出ていますので、売上・利益を増やせないのであれば、給与は増やせないわけです。
高い給与を出せば人が来る?実際の数字との違い
「人が足りないなら給与を上げればいい」というのが一般的な経済学者の意見かと思います。逆から言えば給与が高いところほど、人手不足ではないということが言えるのではないでしょうか。それは本当でしょうか?
バイトルが出している有効求人倍率のページがあります(https://www.baitoru.com/solution/column/effective-job-offers-ratio-ranking/)。こちらを見てみると、有効求人倍率が高いのは土木建築系が主体となっています。土木建築系は時給も高い事で知られていますが、人手不足です。もっとわかりやすいのが有効求人倍率が低い業種を見てみると、事務系が多くなっています。一般事務など、その昔は女性がメインで働いていた職種であり、給与が低いことで有名な職種です。
つまり、一般的に言われている高い給与を出せば人手不足を解消できるというのは、実際の数字と矛盾があるのです。不安定な美術系、もしくは給与の低い事務系が人気という、現実と理論が矛盾しているのが現状です。
経営者が見ているものとは?
経営者にも色んな人がいます。しかし多くの経営者は成功の可能性と失敗のリスクを考えています。例えば時給を上げれば本当に人材が来るのか?人材が来なかった場合、その損失はどうやって穴埋めするのか?採用のための費用はどのくらい出せるのか?などです。経済学者はそのようなリスクはありませんから、簡単に時給を上げればいいと言えますが、経営者は自分の法人も生活もかかっている決断になります。
最悪、経営者は失敗すれば倒産することになります。借り入れがあれば自己破産もあります。そのような状況での決断はかなり重くなるのはおわかりでしょう。論理的にはその通りのことでも、本当にそうなるのかどうか、テストしながらリスク管理していくのです。
経営者はリスクを見ている、これが経済学者との違いです。
まとめ
- ニセコの例から考える、なぜ時給をあげられないのか
- 時給が高ければ人が来るはずなのに、逆転現象が起きている
- 経営者は常に失敗したときのリスクを考えている
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
兵庫県伊丹市出身
2006年、立命館大学経営学部卒業後、パソコンソフトの卸売会社、総合商社子会社に就職し、2008年に独立。
2011年頃からSEO対策・アフィリエイト用の文章制作から、独学でリスティング広告やアクセス解析、SNS広告などを学び、サービスを展開。
短期大学の情報処理講師や職業訓練校のWebサイト制作クラス・ECマーケティングクラスなどで講師を担当。
現在は株式会社キヨスル代表取締役として、Webマーケティングをデザインすることでクライアントのビジネスに貢献する。
その他の記事
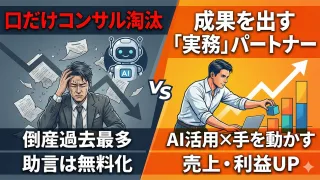 Webマーケティングラジオ2026年1月19日「口だけコンサル」は淘汰される?過去最多の倒産から見るコンサルティングの未来
Webマーケティングラジオ2026年1月19日「口だけコンサル」は淘汰される?過去最多の倒産から見るコンサルティングの未来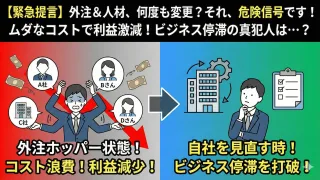 BtoB向け施策2026年1月12日成果が出ないのはパートナーのせい?「外注ホッパー」が陥るビジネスの罠
BtoB向け施策2026年1月12日成果が出ないのはパートナーのせい?「外注ホッパー」が陥るビジネスの罠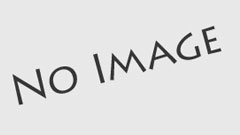 お知らせ2026年1月5日2026年ご挨拶
お知らせ2026年1月5日2026年ご挨拶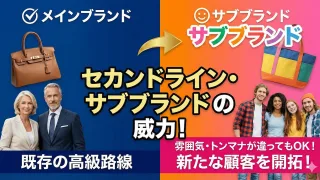 Webマーケティングラジオ2026年1月5日「セカンドライン」で考える新商品・新事業
Webマーケティングラジオ2026年1月5日「セカンドライン」で考える新商品・新事業