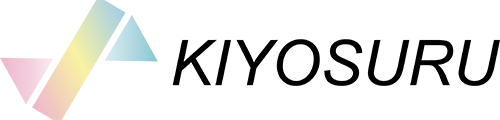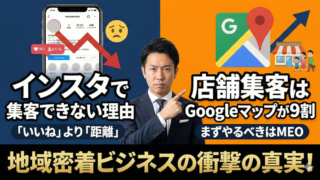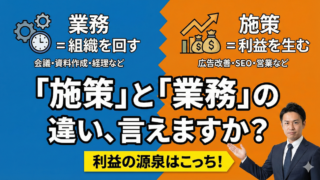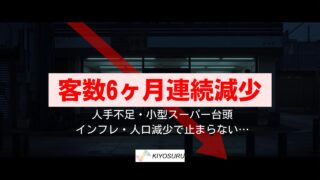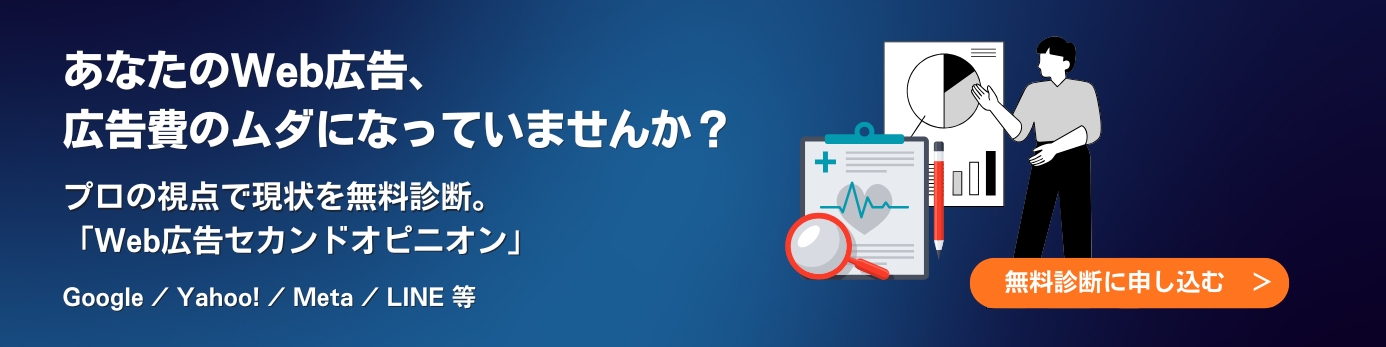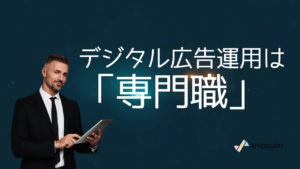話題のMeta広告は今後も活用すべきか?詐欺広告問題とブランド毀損リスク
FacebookやInstagramといったMeta広告について、「詐欺広告」の話題が大きく取り上げられました。堀江さんや前澤さんなど、著名な経営者の方々が無断で広告に利用されるなど、その問題は日本国内でも取り上げられています。このような状況下で、私たちマーケターとして、Meta広告は利用すべきなのでしょうか。
特に企業ブランドへの影響という部分を考えたほうが良いのではないでしょうか。
詐欺広告による収益とプラットフォームの信頼性
Meta広告で、詐欺広告が長期間にわたり掲載され、それがMetaの年間売上の一部(約10%、160億ドル相当)を構成していたという話が表面化しました。詐欺広告の種類としては詐欺的なECサイトや違法な投資スキーム、オンライン賭博などがあるそうです。
(参考:米メタ、詐欺広告などで巨額収益か 1日150億件表示=内部文書 | ロイター)
もちろん、プラットフォーム自体が悪いわけではありませんし、Meta広告がトラフィック獲得や認知拡大において依然として高い効果を持っていることは事実です。しかし、詐欺広告が出ているとわかっているメディアに広告を出してもよいのでしょうか?
マーケターが懸念すべき「ブランド毀損」のリスク
この問題の本質は、詐欺広告の近くに、「自社の広告が表示されること、そしてそれがどのような影響を与えるか」です。Meta広告の利用を続けるにあたり、最も懸念すべきなのは「ブランド毀損(ブランド・リスク)」です。
- ブランドの価値低下:自社の広告が、詐欺的な広告と隣接して表示された場合にブランド毀損の可能性があります。ユーザーは「この企業も詐欺広告と同じなのでは?」と認識する可能性があります。
- ハイブランドほど慎重に:特に高価格・高品質な製品を扱う企業や、ブランド力を最優先するハイブランド企業などはよく考えた方が良いでしょう。もし広告の目的が「ブランドリフト(ブランド価値の向上)」であるならば、一時的にMeta広告の出稿を停止することも検討すべきでしょう。
ブランド毀損リスクはMeta広告だけではない
このブランド毀損のリスクは、実はMeta広告に限定された話ではありません。その他のデジタル広告でもありうる問題です。たとえば、Google広告のディスプレイネットワークでは、以下のようなセンシティブな話題を扱うウェブサイトにも広告が表示される可能性があります。
- 暴力、成人向けコンテンツ
- 特定の宗教や政治的なトピック
- 戦争に関する話題
自社と関連性の低い、あるいは企業理念に反するコンテンツの近くに広告が表示されることで、意図せずブランドイメージが損なわれる場合があります。さらに、ドメインパーキングや、ユーザーに見えない場所での表示といった問題もあります。これらは無駄な広告費の支出となり、間接的にブランド毀損になる可能性があります。
ブランドを守るための具体的な対策
Meta広告の問題ブランドを守りながらデジタル広告を活用するために、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか?できることとして、下記の方法があります。
- コンテンツの適合性を設定する:Google広告などでは、「コンテンツの適合性」設定から、宗教や政治といったセンシティブなトピックを扱うサイトへの表示を事前に除外できます。
- 外部のアドフラウド対策ツールを活用する:アドベリフィケーションなどのツールを活用することで、詐欺的な広告表示(アドフラウド)を検知し、自社のブランドを守る対策を講じることができます。
- ホワイトリスト形式での配信を検討する:配信先を広範囲に設定し、後から問題のあるサイトを除外する「ブラックリスト形式」ではなく、あらかじめ信頼できるサイトを選定する「ホワイトリスト形式」を導入するのも有効な手段です。リーチは狭くなりますが、ブランドを最優先する場合はこの方法が最も安全です。
メタ広告は効果的なツールであるため、すぐに利用をやめる必要はありませんが、ブランド価値を守るという視点を持ち、これらの対策を講じながら運用していくことが重要です。
投稿者プロフィール